2021年08月10日 (火曜日)
News Diet(ニュースダイエット)(情報があふれる世界でよりよく生きる方法)を読んで
★【情報入手の断捨離】新聞やテレビ、インターネット、スマホでの情報過多の時代に取捨選択の重要性を感じる
で書きましたが最近の自分のスマホ中毒というかどちらかというと情報中毒、質の問題などで少しいろいろ考える必要あるな、と思っていくつか本を買いましてその一つです。
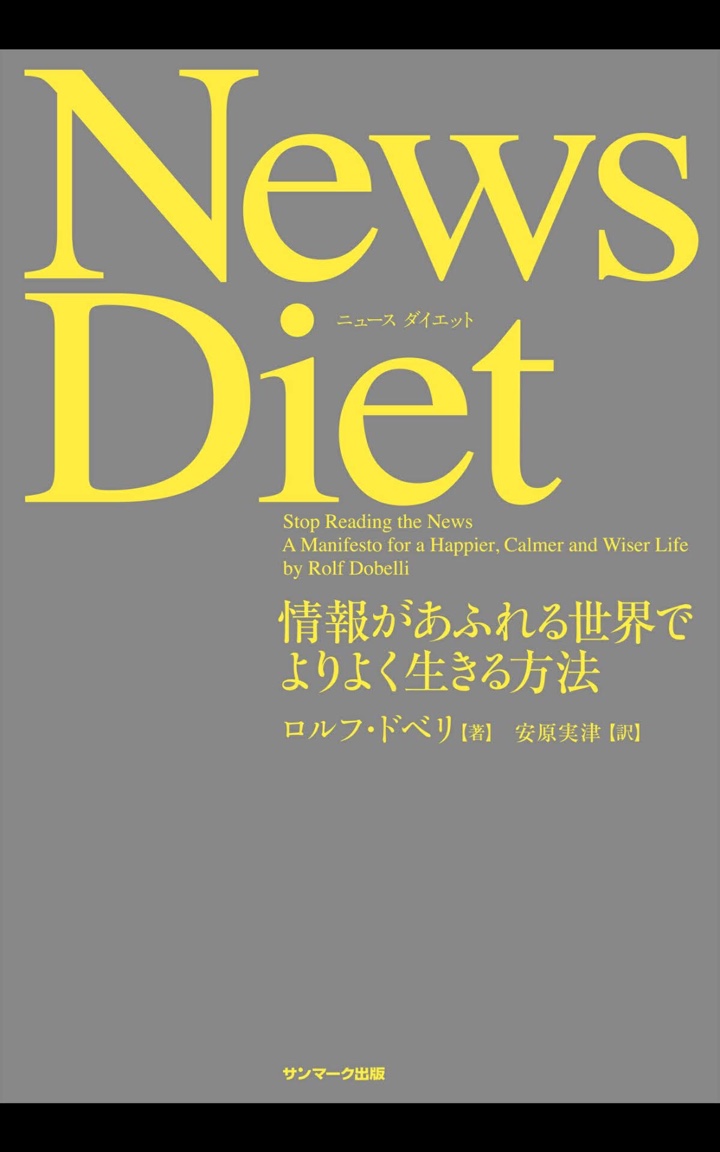
News Diet Kindle版 ロルフ・ドベリ (著), 安原 実津 (翻訳)
です。
読んでいて気になった所を引用します。
「大げさに愚痴をこぼすのはやめよう。そんなことをしても何もならない。ストア派の見解によれば、世界は二つの領域に分かれている。
一方には、私たちが影響を及ぼすことのできるものがある。もう一方には、私たちの介入から逃れているものがある。「自分がコントロールできないもの」について心配をしても、なんの約にも立たないし、ほとんど馬鹿げているとさえ言ってもいい。それなのに、ものごとの大部分はそちらの領域に属している。わたしたちがニュースメディアで読む出来事は特にそうだ。
だから私たちは「自分にできること」だけをして、コントロールできない残りのものは無視しよう。」
よくよく考えれば流れてくるニュースをいちいち気にする必要、ないよね・・・・
ひとつ目。大げさに愚痴をこぼすのはやめよう。そんなことをしてもなんにもならない。 ストア派の見解によれば、世界はふたつの領域に分かれている。一方には、私たちが影響を及ぼすことのできるものがある。もう一方には、私たちの介入から逃れているものがある。「自分がコントロールできないもの」について心配をしても、なんの役にも立たないし、ほとんど馬鹿げているとさえ言っていい。それなのに、ものごとの大部分はそちらの領域に属している。私たちがニュースメディアで読む出来事は特にそうだ。 だから私たちは「自分にできること」だけをして、コントロールできない残りのものは無視しよう。私たちが影響を及ぼせる、小さな領域の内側で努力をするようにしよう。パンデミックのさなかでも生産的でいられるように。そして、自分の仕事をこれまでどおりきちんとこなすためにも。
確かに私の関係ないニュースに反応しすぎている気がしますね。それに対して感情や考える力使ってどうするの?もっと別の事に思考能力や時間を使った方が良いのでは?と。
「意見というのは、鼻のようなものだ。誰でもひとつは持っている。恍惚としながら最新情報を追いつづけ、あたかも未来を嗅ぎとれるかのようなふりをする──そんなもったいぶったことはしなくていい。あなたの「本日の意見」が真実の的を射る確率は、非常に低い。」
マジで流れてるニュースに対して一喜一憂する必要もない、そして流れてくるニュースの内容は本当たいした事がないものばかり。その情報を元に考えたところで確かに真実の的を射る確率は低い。
「新型コロナは、メディアが豊富な知識を持っているわけではないということを明確にしてくれた。念のためにつけ加えておくと、このことが当てはまるのは新型コロナに関してだけではない。何に対してもそうだ。」
これ、本当そうだよな。基本的なメディアはまず豊富な知識なんか持っていない。
「読者の方から感謝を述べられることが最も多かったのは、「能力の輪」についての章だ。 新聞を広げたり、ニュースウェブサイトに飛びついたり、あるいはどこかのニュースフィードを購読したりする前に、あなたはまず自分個人の「能力の輪」を明確にしなくてはならない。「能力の輪」が明確になれば、あなたに関連のあるものとないものとの区別ができる。その輪の内側に入るものはあなたにとって関連があるが、それ以外はすべてあっさりと無視してしまってかまわない。「能力の輪」の外側にあるニュース記事を消費したところで、あなたが得るものは何もない。時間が無駄になるだけだ。」
いろいろな本に書いてある事ではあるけれど、本当自分をちゃんと分析し、把握しておく必要あるよね・・・・・
「「ニュース」の対極に位置するのは、長い形式のもの──新聞や雑誌の長文記事、エッセー、特集記事、ルポルタージュ、ドキュメンタリー番組、本などだ。それらの多くが伝える内容は有益で、新しい知識やものごとの背景情報をもたらしてくれる。」
考えてみればインターネット、というよりかはSNS、特にTwitterをやるようになってからかな。細かいニュースまで見るようになったの。それまでは長文記事の新聞記事や本や技術記事とか見ていたと思う。
「そして別の本をはさむことなく、つづけてもう一度読み返す。二度読んだときに得られる効果は、一度しか読まないときの倍どころではない。私の経験から言えば、効果はほぼ一〇倍にはね上がる。「二度読み」の効果の高さは、もちろん長文記事にも当てはまる。」
「何を探すかを決めるのは、あなたでなくてはならない。進む道を定めるのは、あなたでなくてはならない。ニュースメディアにあなたの注意を操らせてはならない。」
「なぜなら世界でニュースが報じられると、その内容は人々の「基本認識」の一部になるからだ。だが、周りよりも優位に立つには、(a)正しく、(b)まだ人々の基本認識として成立していない「ものごとのつながり」を見きわめなくてはならない。手に入れた時間を使って集中して思考をめぐらせれば、あなたはニュースを消費している仲間たちには見えていない「ものごとのつながり」をさぐり当てることができる。」
「最初のインターネットブラウザが市場に登場したのは、一九九三年一一月一一日のことだった──おそらく原爆に次いで最も影響の大きい二〇世紀の発明品だ。 そのブラウザの名前をご存じだろうか? 「モザイク」である。聞いたことがなくても仕方がない。この出来事がニュースで取り上げられることはなかったからだ。 そのかわり、そのころのドイツのテレビニュースでは、政党助成制度改革についてや、イスラエルのラビン首相がアメリカのクリントン大統領を訪問したことや、ローマ教皇が肩関節を折ったことなどが報じられていた。つまりニュースジャーナリストもニュースの消費者も、重要な出来事を見出す感覚器官は持ちあわせていないのだ。 それどころか、ニュースの重要度とメディアの関心の高さは反比例しているといってもいい。ニュースでさかんに報じられる出来事ほど、重要度は低い。」
これは凄い納得した。インターネット(ブラウザ)という超凄いものが生まれた当初は一般的なニュースには取り上げられていなかったわけだ。書いてあるとおりジャーナリストな方々もそのニュースを見る方も全然見る目がない、という事。
*今も未来を変えるような凄い話が流れてるかもしれないけど・・・・・それに目をつけられる人は数えるぐらいしかいなさそうよね・・・・・
・・・とはいえ
これ思い出す>元財務大臣、多国籍企業の社長、オックスフォードの学生、清掃作業員の4グループに10年後の世界経済を予測させたそうです。最高得点を出したのは清掃作業員のグループでした。最低点は元財務大臣 / “なぜ経済学者は信用されないのか?──『絶望を希望に変え…” https://t.co/8RXKEc96mY
— 封神龍(手洗いうがい推奨仕様) (@yuumediatown) May 24, 2020
>元財務大臣、多国籍企業の社長、オックスフォードの学生、清掃作業員の4グループに10年後の世界経済を予測させた。最高得点は清掃作業員でした。最低点は元財務大臣。専門家は意図的に嘘の情報を流す>クーリエ ジャポン 2015年05月号「「頭がいい人」の条件が変わった。」 https://t.co/BJJ79JHIxy
— 封神龍(手洗いうがい推奨仕様) (@yuumediatown) August 1, 2019
意図的に嘘を流すのはともかくとしてやっぱり専門家でも予測は難しいわけで・・・・・
微妙に矛盾するけど自分のゾーンにはまるものを精査していけばそのうちこれは凄い事になるのでは?というニュースにたどり着く事もありそう。
目指すべきは真のプロフェッショナルか。
「報じられていない出来事の方が、重要度が高い場合が多いのだ!~中略~あなたにとっての重要事項を、メディアから見た重要事項と混同してはならない。メディアにとっては、読者の注意を引くものは全て重要なのだ。ニュース産業におけるビジネスモデルの核をなすのは、この欺瞞である。メディアは、私達とは無関係のニュースを重要な事と称して私達に提供しているのだ」
「それなしでは生きられないほど重要なニュースなど存在しない。数え切れないほどのニュースよりも、たった一冊の良書の方が何千倍もあなたの人生と健康の為になる」
「ウォーレン・バフェットはこんな人生訓を持っている。「自分の能力の輪を知り、そのなかに、とどまる事。輪の大きさはそれほど大事ではない。大事なのは輪の境界がどこにあるかをきちんと把握する事だ」」
やはりここでも自分についての把握の話。
輪の中の情報は必要、輪の外の情報は無視で構わない。余計な情報は集中力を低下させる原因にもなる。
「ニュースを消費すると、頭の中に誤ったリスクマップができあがる。だからニュースをもとに決断を下すのはやめた方がいい。実際のリスクを元にして決断を下そう。それらが見つかるのは本や統計や、きちんと調査されて書かれた長文記事の中だ」
例としては墜落事故が起きたら、飛行機に乗るのを控えるのか?墜落事故が起きたからといって自分の行動を変える必要はまったくない。
「ニュースを読む度に、あなたは自分の思考をもう一度かき集めなければならない。仕事はどこまで進んでいただろう?あの文章はどこに保存した?ニュースがあなたの注意を独占する前に、次に取りかかろうとしていた事は何だっただろう?逸れた注意を元に戻すだけに、毎回2~3分の時間が奪われている(なんだかんだで1日あたり1時間半を無駄にしている)」
まあニュースというよりこれはTwitterも当てはまる気が・・・・・
「古代ローマの偉大な哲学者、セネカは既に2000年前にこう疑問を呈している。「お金の事になると私達は倹約家になる。それなのに、時間に関してはとんでもない浪費家になる----私達が本当に倹約すべき唯一の財産は時間だというのに」」
2000年前に既にこの境地
「悪い事は、よいことよりも重要だと感じられる。そのためネガティブな情報は、ポジティブな情報のおよそ二倍強く私達に作用する。この現象を心理学者は「ネガティビティ・バイアス」と呼んでいる」
「慢性的なストレスは、消化不良や成長阻害(細胞や髪や骨などに対して)、いらだちを引き起こすほか、感染症に対する抵抗力を弱める原因にもなる。ニュースの消費によって不安症状が現れたり、攻撃性が高まったり、ものごとを見る視野が狭くなったり、感情的に鈍感になったりといった副作用が生じる事もある」
この辺り見ていると
なるほどな
— 大波コナミ_bot(cv:幡宮かのこ) (@moja_cos) August 9, 2021
TV視聴と早めに訣別できた自分は精神的には結構健全かもしれん pic.twitter.com/TFedAj2jfR
メディアは不安を煽らないと商売に繋がらないため、どこも不安を煽りますね。
— ケイ THE 雑学📚ただ学術的雑学を呟くだけの人 (@mikaitabi) May 8, 2020
①人は不安を感じるとストレスを受ける
②ストレスを受けると誘惑に弱くなる
③誘惑に弱くなると消費でストレスを解消したくなる
④消費するために広告を見る
⑤消費することでストレスが一時的に解消される
の繰り返し。
を思い出しますね・・・・・
あとこれ。
https://twitter.com/imaicn21/status/1422940854524669958
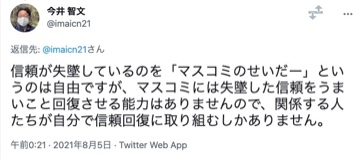
「今井 智文 @imaicn21
信頼が失墜しているのを「マスコミのせいだー」というのは自由ですが、マスコミには失墜した信頼をうまいこと回復させる能力はありませんので、関係する人たちが自分で信頼回復に取り組むしかありません。」
└現在は削除されてしまっています。
凄いよな、これはHPVワクチンについてもうマスコミが煽って煽って先進諸国の中でも摂取率を最低にしたあげく結果的には年間数千人殺してるわけで、私達は面白おかしくは煽るけど訂正報道は絶対にしません、といってるようなものでこういう連中が新聞業界内にはいまくるわけで、この発言に対して報道がらみの方々は一部を除きほぼ否定なし。
やべぇ事、言ってしまった、という事で削除したのでしょうがこれが本音。
最終的には
【おわび】一連の議論について、賛否両方のご意見をいただく一方、議論の冒頭となったツイートについては皆様から「内容が無礼だ」などのご指摘を受けました。文章を書いて生きていく者として、批判は謙虚に受け止めます。ツイート3件については撤回、削除することを決めました。(1/n)
— 今井 智文 (@imaicn21) August 7, 2021
な感じで逃走か・・・・・
話を戻しまして本の話。
「私達は「自分のお気に入りの見解に反する情報」は自動的に排除する一方で、「自分の確信を後押しする情報」には敏感になる。それが数字の並び方ならなんの問題もない。危険なのは、政治的な見解や、お金がかかわっている時だ。」
「何があろうと、イデオロギーや教義(宗教や宗派の教え)には近寄らない方がいい。あなたが少しでも共感を持てるようなイデオロギーや教義がある場合は特に要注意だ。イデオロギーを持つ事が間違いなのは確実で、あなたの世界観が狭まって、結果的にはお粗末な決断をしてしまう。」
いわゆる左右極端な方々がやべぇ発言やとんちんかんな発言を繰り返すのはこういう事なんだろうなぁ・・・・・
「ニュースを消費すると、脳の生理的な構造が徐々に変化する。短い情報にざっと目を通すときに必要な脳の領域を鍛える事になる。そしてそれに伴い、長い文章を読むことや、思考を司る回路は退化する。あなたはもう一度、疲れを感じずに本や長文記事が読めるようになりたいだろうか?だったらニュースを消費するのは今すぐに止めておくことだ。」
これ、驚きだった。普段の情報摂取状況によって脳の構造が変化、ニュースを消費し続けると長文や本を読むのが苦手になってしまう可能性も、と。
「自分ではコントロールできない曖昧な情報に脳が出くわすと、私達は時間とともに犠牲者の役割を受け入れるようになる。行動を起こそうとする意欲が失われ、受け身になってしまうのだ。この現象は、学術的には「学習性無力感」と呼ばれている」
前に
★心理学でっていう「学習性無力感」(2008年05月06日 (火曜日))
このブログでも書きましたね。
「ニュースを眺めるのではなく、お金を寄付しよう。自分の手で水用ポンプを組み立てる為に、サハラ砂漠まで出かけて行くのはやめておこう。この善意の勘違いは「ボランティアの浅はかな考え」という呼び名で知られている。あなたが自分で設置できる給水所は一日に1箇所程度だろう。けれどもあなたが普段の仕事(つまりあなたの「能力の輪」の内側にある事を)をこなして、稼いだお金をアフリカに送れば、そのお金で1日に100箇所の給水所が出来上がる。お金を送った方がずっと世界の貧しい人の助けになるのだ。」
自分の本領発揮して世界を救おう、と。
とにかくフォアグラ作る為のアヒルじゃないけど情報を強制的に流し込むのはよくなさそう。
今すぐに、はできないだろうけど徐々にニュースの過剰摂取的なのは抑えていきたいと思いました。仕事の都合上、世の中の普通の人が見ているニュースを何も知らない、というのも不味いのでね。
Posted by 封神龍(酒) at 2021年08月10日 16:31 | 【所属カテゴリ: お勧め商品【本・】2】【コメントについて】【トラッくバックについて】【RSS登録について】
--
--
