2021年11月02日 (火曜日)
Amazonで「スマホ脳(新潮新書) Kindle版」をダウンロード購入して読み終えた
だいぶ前に買った奴ですが
スマホ脳(新潮新書) Kindle版
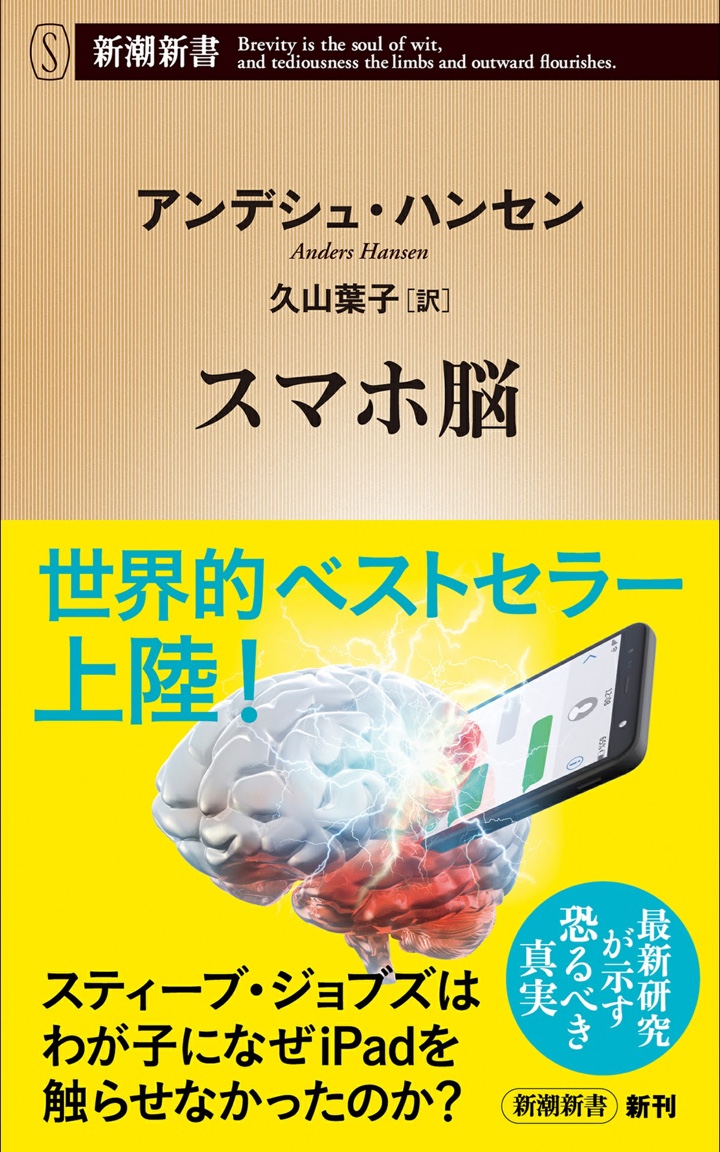
をようやく読み終えました。気になった所を引用しますが。
「スウェーデンではなんと、大人の9人に1人以上が抗うつ剤を服用しているし、同様の統計が多くの国で見られる。この増加は、ここ数十年で私達が裕福になり、GDPが上昇するにつれて起きた。良い暮らしができるようになったのにむしろ不健康になるなんて、いったいどういうわけだろう?」
本の最後の方には結論的なのがありますが、インターネット、スマホ、特にSNSの影響が大きそう。
「睡眠、運動、そして他者との関わりが精神的な不調から身を守る3つの重要な要素だ。それは研究でもはっきり示されている。それらが減ると、調子が悪くなる。守ってくれる要素がなくなるからだ。だから生活は快適になったのに、なぜ精神状態が悪くなるのか理解出来るようになる。」
生物としての行動を逸脱してもろくな事はない、って事ですかねぇ。
「ネガティブな感情はポジティブな感情に勝る。人類の歴史の中で、負の感情は脅威に結びつくことが多かった。そして脅威には即座に対処しなければいけない。食べたり飲んだり、眠ったり交尾したりは先延ばしに出来るが、脅威への対処は先延ばしに出来ない。強いストレスや心配ごとがあると、それ以外のことを考えられなくなるのはそれが原因だ。」
ネガティブな情報の方が人の気をひけるのは本能的なものもあるんですね、というかそりゃそうだよね。
「つまり強いストレスに晒されると「闘争か逃走か」という選択肢しかなくなり、緻密なプレーをする余裕はなくなる。迅速な判断を下そうと「エラーチェックモード」に入った脳にとって、最優先なのは瞬時に問題を解決する事だ。社会的に緻密な行動ではなく。すると自分を取り巻く環境内で発見したエラーに厳しく反応してしまう。その結果、些細なことでも強い苛立ちを感じるようになるのだ。「何で靴下が床に転がっているんだ?」というように。強いストレスにさらされると、問題に気を配る余裕もなくなるので、堪忍袋の緒も切れやすくなる。一方。心が満ち足りていると、人は警戒を解く」
「未来を予測する能力は、私達人間が持つ一番重要な特性かもしれないが、おかげで見たくないものまで想像出来てしまう。首になるかもしれない、捨てられるかもしれない、家のローンを払えなくなるかもしれない。そんな理由でストレスのシステムが作動するのは知性を得た代償だ。現実の脅威と想像上の脅威を見分ける事が、脳にはできないのだ。」
こういう仕組みがわかってくると・・・・いろいろと考えさせられるものがあります。
「ドーパミンの最も重要な役割は私達を元気にすることではなく、何に集中するかを選択させることだ。つまり、人間の原動力といえる。お腹が空いてる時にはテーブルに食べ物が出てきたら、それを見ているだけでドーパミンの量が増える。つまり増えるのは食べている最中ではない。その食べ物を食べるという選択をさせるためにドーパミンはあなたにささやく。「さあ、これに集中しろ」。ドーパミンが、満足感を与えると言うより行動を促すのは、満足感はどこから来るのだろうか。それは「体内のモルヒネ」であるエンドルフィンが大きな役割をはたしているようだ。ドーパミンは目の前にある美味しい物を食べるように仕向けてくるが、それを美味しいと感じさせるのはエンドルフィンだ。」
「周囲の環境を理解する程、生き延びられる可能性が高める---その結果、自然は人間に、新しい情報を探そうとする本能を与えた。この本能の裏にある脳内物質は何だろうか?もうおわかりだろう。そう、ドーパミンだ。新しい事を学ぶと脳はドーパミンを放出する。それだけではない、ドーパミンのおかげで人間はもっと詳しく学びたいと思うのだ。」
こういうのも本能なのね・・・・・・
「脳にしてみれば、もらえるまでの過程が目当てなのであって、その過程というのは、不確かな未来への期待でできている。」
「脳には切り変え時間が必要で、さっきまでやっていた作業に残っている状態を専門用語で「注意残余(Attention residue)」と呼ぶ。ほんの数秒メールに費やしただけでも、犠牲になるのは数秒以上だ。切替時間の長さを確定する事はできないが、ある実験が示唆している。集中する先を切り変えた後、再び元の作業に100%集中できるまでには何分も時間がかかるという。しかし、マルチタスクが苦手な人ばかりではない。現実には並行して複数の作業ができる人もいる。ほんの一握りながらスーマーマルチタスカーと呼ばれる人がいるのだ(人口の1~2%)と考えられている」
「マルチタスクを頻繁にやる人は、些末な情報を選り分けて無視するのが苦手なようだ。つまり、「常に気が散る人はほぼ確実に、脳が最適な状態で動かなくなる」」
「大学生500人の記憶力と集中力を調査すると、スマホを教室の外に置いた学生の方が、サイレントモードにしてポケットにしまった学生よりも良い結果がでた。学生自身はスマホの存在に影響を受けていると思ってもいないのに、結果が事実を物語っている。ポケットに入っているだけで集中力が阻害されるのだ。同じ現象が他の複数の実験にも見られた。そのひとつに、800人にコンピューター上で集中力を要する問題をやらせるというものがあった。結果、スマホを別室に置いてきた被験者は、サイレントモードにしたスマホをポケットに入れていた被験者よりも成績がよかった。実験報告書のタイトルが実験の結果を物語っている。「脳は弱る---スマートフォンの存在がわずかにでもあれば、認知能力の容量が減る」」
スマホの存在、ここまで人間に影響が・・・・落ち着かなくなるわけですね、スマホを意識するだけで。
「手書きメモはPCに勝る。これがどういう理由によるものなのか正確にはわからないが、パソコンでノートをとると、聴いた言葉をそのまま入力するだけになるからかもしれない、と研究者は推測する。ペンだとキーボードほど早く書けないため、何をメモするか優先順位をつける事になる。つまり、手書きの場合はいったん情報を処理する必要があり、内容を吸収しやすくなるのだ」
実感する事があります・・・最近、仕事で紙の書類にたくさんの文字を書く必要があり、それはそれでいいとして、パソコンで似たような事を入力していた時に比べ、その書いた文字のことがパソコンで入力したものに比べ思い出しやすくなってるんですよね・・・・何かを覚える、勉強するなら入力より、紙に書いた方が良さそう。これも体感的、なんとなく的には分かっていたことではありますが・・・・
「どのみち保存されるのに、なぜそれにエネルギーを浪費しないといけない?脳はそう考えるようだ。驚く事でもない。作業の一部をパソコンに任せられるなら、そうするに決まっている。保存されるとわかっていれば、情報そのものよりも、情報がどこにあるかを覚えておく方がいい。被験者達がワード文書に文を書き留めた実験では、1つの文を1つのファイルにして異なったフォルダに保存してもらったが、翌日になると文の内容はあまり覚えていなかった。一方、どのフォルダにどの文書ファイルを入れたかは覚えていたのだ」
「グーグル効果とかデジタル性健忘と呼ばれるのは、別の場所に保存されているからと、脳が自分では覚えようとしない現象だ。脳は情報そのものよりも、その情報がどこにあるかを優先して記憶する。」
とはいえ、自分ではこのブログ、日記として書いているけど、1日の最後、もしくは次の日になっちゃうけど、頭の中を整理しつつ文字を入力するという行為は脳にはよさげな気がしないでもない。多分紙に書いた方がなお良いのだろうけど。それが長期的な記憶にとって良いかはまた違う話なのだろうけどね。
「判明したのは、写真を撮っていない作品はよく覚えていたが、写真を撮った作品はそれほど記憶に残っていなかったことだ。パソコンに保存される文章を覚えようとしないのと同じで、写真に撮ったものは記憶に残そうとしないのだ。脳は近道を選ぶ。「写真で見られるんだから、記憶には残さなくていいじゃないか」
これも聞いたことがある。写真をとにかく撮りまくってた旅行とそうでない旅行、印象というか記憶に残ってるのはあまり写真に撮らなかった方、だと。こういうのももう研究とかでその理由というかが実証されているのか。
「体重が気になる人は、夜遅くまでスマホを使うと食欲が増進する可能性があることを知っておいた方がいいだろう。ブルーライトの影響を受けるのは催眠を促すメラトニンだけではない。ストレスホルモンのコルチゾールと空腹ホルモンのグレリンの量も増やすのだ。グレリンは食欲を増進させるだけではなく、身体に脂肪を貯めやすくもする。」
気をつけよう・・・・・
「人と会うのの次に活性化するのは演劇鑑賞だった。映画鑑賞に同じ効果はなく、ミラーニューロンは活性化されるものの、目の前で何かが起きている時ほどの強さではない。映画のスクリーンやパソコンのモニターで何かを見ても、他人の考えや気持ちを本能的に理解する生物学的メカニズムに同じだけの影響はないというわけだ。」
やはり人間、移動し、物や人に触れあい、お話したり意思疎通したりで脳の反応が大きくなるんですね。
「SNS上で拡散された10万件以上のニュースを調査したところ、フェイクニュースの方が多く拡散されていただけではなく、拡散速度も速い事がわかった。一方で正確なニュースは、フェイクニュースと同程度に拡散されるまで6倍の時間がかかっていた」
だから最近は個人的には変なニュースはリツイートとか、すぐにはしないで様子見しています。
「就学前の子供を対象にした研究では、手で、つまり紙とペンで書くという運動能力が、文字を読む能力とも深く関わっているのが示されている」
子供はキーボード入力よりとにかく紙に文字、書いた方がいいと。これ、大人でもそうだろな。
「報酬を先延ばしにできなければ、上達に時間がかかるようなことを学べなくなる。クラシック系の楽器を習う生徒の数が著しく減ったのも1つの兆候だ。ある音楽教師にその理由を尋ねたところ、こんな答えが返ってきた。「今の子供は即座に手に入るごほうびに慣れているから、すぐに上達できないとやめてしまうんです」」
「この調査では、子供よりもティーンエイジャーの方が、スマホやタブレット端末の使用と心の不調が結びついている事がわかった。考えられる説明としては、子供はゲームで遊んだり、動画を観たりするが、ティーンエイジャーはSNSを使うからだろう。ここまで見てきたとおり、SNSは私達の精神状態に影響を及ぼす。常に他人と比較することがストレスになり、心に不調をきたすのだ。」
私も長らくインターネットを使っていますが、生活的に何か変ってきたと思えるのはスマホによるSNSが使えるようになってからかな・・・・SNSの前の時代はホームページやメーリングリスト、そういったので情報得ていたと思いますが、中毒性なものがそこまであったかはともかくパソコンの前に来ないとそれが出来ませんでしたから。今はスマホがあり年中、ネットに繋がっていてなおかつ、中毒性のあるSNSがある。
で、携帯でSNSができるといってもガラケーではやはり使いにくい部分がありそこまではまり込めない、そしてスマホの初期もそう。しかし今やどんな安い端末でもTwitterやFacebook、Instagramなどをやる分には性能的には全然問題ないし・・・・
気がついたらスマホ、見てますよね。昔はもっと本や新聞を読んでいた。それに比べてSNSで流れてくる情報は細切れで有用なものはあるでしょうけど短い文章では専門的な知識も得にくい。前に読んだ
★News Diet(ニュースダイエット)(情報があふれる世界でよりよく生きる方法)を読んで(2021年08月10日 (火曜日))
にも書いてありました。
「運動を取り入れる事で元気に活動し、脳の動きをよくしようとする人に何百人も会ってきたが、そこで気づいたことがある。皆が最も高く評価しているのは集中力アップではない。ストレスや不安への効果だ。」
鬱に対して体を動かす、運動がいいとは聞いたことありますが・・・・・
「今でも狩猟採集民として」原始的な農耕社会に暮らす部族を調査すると、私達の祖先は毎日14000~18000歩、歩いていたと思われる。今の私達は1日5000歩にも満たない。そしてその数字は10年ごとに減っている。スウェーデン人の平均的な体力は90年代から11%下がり、現在は大人の半数近くが、健康に害が及ぶほど身体のコンディションが悪い。特に悪いのは若い人達だ。14歳の運動量は2000年頃と比べると女子で24%、男子で30%減っている。」
私も今の仕事でなければ確かに1日5000歩もいかないかもな・・・・今は10000~18000歩ぐらい歩きますが・・・・
「スマホやパソコンに多くのことを任せるにつれ、それを操作する以外の知能が次第に失われるのではと怖くなる。でももしかすると、知能の容量を開放して、何か別の大事な事に使えるようになるのでは?GPSが自分の代わりに目的地を見つけてくれれば、集中してPodcastを聴いたり仕事のことを考えたりする時間ができるはず。そう、おそらくそうだ。だが何もかも外部委託するわけにはいかない。世界と接し、相手を批評し、目の前の情報を精査するためには、ある程度の知識が必要だ。ましてや今は、よりいっそう複雑な時代なのだ。複雑さを極め行く社会は、私達を賢明にする。フリン効果だ。だが、私達が愚かになる可能性もあるような気がする。自分で考えるのをパソコンやスマホに任せてしまうこともできるからだ。これがまさしく、北欧のIQ低下傾向に繋がっているのだろう」
個人的にはパソコンやインターネットで便利にはなった、ただもう少しアナログ的なのに回帰した方がいいのかな?と。不便でも、その過程が脳にはいいのかもしれないし。
★【情報入手の断捨離】新聞やテレビ、インターネット、スマホでの情報過多の時代に取捨選択の重要性を感じる(2021年08月10日 (火曜日))
こういうふうに思ったのも自然な流れなのかな。
本の最後にはこれらを踏まえてのアドバイスがあり
・自分のスマホ利用時間を知ろう
・目覚まし時計と腕時計を買おう
└スマホでなくてもいい機能はスマホを使わないようにしよう
・毎日1~2時間、スマホの電源を切ろう
・プッシュ通知はオフにしよう
・スマホの画面をモノクロ表示にしよう
└ドーパミンの排出量が少なくなる
・運転中はサイレントモードに
職場では
・集中力が必要な作業をする時はスマホを隣の部屋に置こう
・チャットやメールをチェックする時間を決めよう
人に会っているときは
・スマホをマナーモードにして遠ざけておき、一緒にいる相手に集中しよう
・スマホを取り出すのは止めよう、周りの人も取り出し始める
子供と若者へ
・教室でスマホは禁止
└それでないと学習能力が低下する
・スクリーンタイムを制限し、代わりに別の事をしよう
・良い手本になろう
└私達は相手をまねることで学ぶ。子供は大人がしているようにする。
寝る時には
・電源を切ろう、寝る1時間前には
・寝室にスマホはいれないようにしよう
ストレスの対処法
・運動をしよう
SNS
・積極的に交流したいと思う人だけフォローしよう
・SNSは交流の道具と考え他人の投稿に積極的にコメントしよう
・スマホからSNSをアンインストールしてパソコンだけで使おう
と。
これらを踏まえて自分も少し、行動を変えて行ければいいな・・・・・
Posted by 封神龍(酒) at 2021年11月02日 15:31 | 【所属カテゴリ: お勧め商品【本・】2】【コメントについて】【トラッくバックについて】【RSS登録について】
--
--
